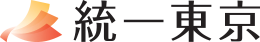台湾でハンドルを握る!日本人ドライバーのための完全ガイド
台湾ドライブの夢を叶えるために:
まず知っておくべき二つの道
台湾の魅力といえば、活気あふれる夜市、息をのむような絶景、そして何より温かい人々との出会いです。しかし、旅の自由度を格段に高めてくれるのが「自分で運転する」という選択でしょう。公共交通機関ではアクセスしにくい秘境や、海岸線をゆくドライブロードなど、車があれば台湾の違った表情を発見できるはず。
一方で、長期滞在となるビジネスパーソンの方々にとっては、この地での生活において、行動範囲を広げたり、業務をスムーズに進める上で「移動の自由」は欠かせません。工業団地や郊外への出張といった際に、車での移動は必須となるでしょう。
「日本と同様に台湾でも車を運転できるといいなぁ」とお考えの皆さまに朗報です。実は、日本の運転免許証を活かして、台湾で運転することが可能です。この記事では、安心してハンドルを握るために必要な手続きと準備をわかりやすくご紹介します。ご自身の滞在スタイルに合わせて、最適な手続きを選びましょう。
Part 1:短期滞在(1年以内)なら「翻訳文」でOK
観光や短期出張などで台湾に入境後1年以内の滞在であれば、日本の運転免許証と、その中国語翻訳文を携帯することで運転が可能です。
必須の「中国語翻訳文」の準備
重要なのは、この翻訳文は自分で作成してはいけないという点です。以下のいずれかの機関が発行したもののみが認められます。
- 日本台湾交流協会(台北事務所または高雄事務所) https://www.koryu.or.jp/
- 日本自動車連盟(JAF) https://jaf.or.jp/
| 項目 | 備考 |
|---|---|
| 日本の運転免許証(原本) | 有効期限内のもの |
| 中国語翻訳文 | 上記指定機関発行のもの(発行日から1年以内が有効とされる) |
| パスポート | 台湾への最終入境日が確認できるもの |
!要注意!
国際運転免許証(ジュネーブ条約に基づくもの)は、台湾では使用できません。また、台湾は右側通行・左ハンドルです。日本と逆であるため、細心の注意が必要です。
Part 2:長期滞在者は「台湾免許証」への切り替えが必須
1年以上の長期滞在を予定されている方が取るべき手続きは、短期旅行者とは異なります。日本の運転免許証を基に無試験での台湾運転免許証への切り替え(外免切替)手続きについて重要事項と実務上の注意点をまとめました。
◆ 切り替えのメリットと必須条件
| 項目 | 条件 | 注意点 |
|---|---|---|
| 取得方法 | 日本の免許があれば、筆記・実技試験は免除されます。 | 無試験で取得できるため、居留証取得後すぐに手続きを推奨。 |
| 申請期限 | 台湾入境の翌日から1年以内 | この期限を過ぎると、改めて試験を受ける必要が生じます。 |
| 居留条件 | 台湾の居留証(ARC)の原本(居留期間が6ヶ月以上のものが必要) | ARCを取得したら、早めに手続きを始めましょう。 |
◇ 申請時に特に注意すべき二大ポイント
1.「滞在証明」の準備 日本の免許取得後に「その国(日本)に3ヶ月以上滞在していたこと」を証明する必要があります。
2. 健康診断の事前受診 申請前に、指定の病院や診療所で身体検査を受け、申請書(普通汽車駕駛執照登記書など)に診断結果を記入してもらう必要があります。
◇ 申請に必要な主な提出書類リスト(監理所での手続き)
| 項目 | 詳細と準備 |
|---|---|
| 申請書 | 監理所備え付け(健康診断の結果記入欄を含む) |
| 台湾の居留証(ARC) | 原本とそのコピー(居留期間6ヶ月以上) |
| 日本の運転免許証 | 原本とそのコピー(有効期限内のもの) |
| 中国語翻訳文 | 上記Part 1で記載の指定機関発行のもの(発行日から1年以内) |
| パスポート | 原本とそのコピー(滞在証明のために旧パスポートが必要な場合あり) |
| 証明写真 | 2〜3枚(監理所指定のサイズに注意) |
| 手数料 | 約200元+健康診断費用 |
Part 3:【実務編】台湾での車調達ガイド:購入 vs リース徹底比較
台湾での生活やビジネスの基盤が整ったら、次なる課題は「移動手段の確保」です。ビジネスパーソンにとって、行動範囲を制限しない車の調達は必須ですが、購入とリース、どちらが賢明でしょうか。駐在期間と会社の経理方針に合わせて最適な方法を見極めましょう。
1. 車両購入 vs カーリース 比較表
| 比較項目 | 車両購入(新車・中古車) | カーリース |
|---|---|---|
| 調達形態 | 法人名義、個人名義(居留証があれば可能) | 法人リースが一般的だが、個人向けリースもあり |
| 契約期間 | 制限なし(所有権は自分/会社) | 一般的に1年~5年 |
| 初期費用 | 高い(頭金、諸費用、税金など) | 安い(保証金や前払い金程度、初期費用ゼロのプランもある) |
| 月々の費用 | ローン支払い(または一括購入費)+維持費(税金、保険、整備)をすべて負担 | リース料に保険・税金・整備費用がほぼ含まれる |
| 処分・売却 | 帰任時に売却手続きが必要。売却損益が発生するリスクあり | 契約満了時に車両を返却するだけ。売却の手間やリスクがない。但し中途解約の場合は違約金が発生するケースもあり。 |
| 台湾での手続き | 車両登録、名義変更、税金申告などをすべて行う必要がある | リース会社がすべて代行するため、手続きは非常に簡便 |
2. 駐在員がリースを推奨する理由
◆ 手間がない: 税金の申告や保険の更新、定期整備の手配をリース会社がすべて請け負ってくれるため、現地での煩雑な事務作業から解放されます。
◆ 経理処理: 法人リースの場合、原則として車両を資産計上する必要がなく、経費として処理できるため、経理処理が簡素化されます。
◆ 帰任が楽: 帰任時に車両の売却先を探したりする手間や、予期せぬ売却損が発生するリスクがなくなります。
3. 購入を選択する場合の留意点
◆ 市場の安定性: 台湾では日本車が圧倒的なシェアを持ち、整備網も広いため、中古車市場での安定性を考えると有利になることが多いです。
◆ 帰任時の手間: 帰任が近づいたら、売却の時期と価格を慎重に見極める必要があります。日本の市場とは異なるため、売却価格が不安定になりやすい点に注意が必要です。
いずれの方法を選択するにせよ、契約前には必ず保険(特に自損・対物)や年間走行距離制限などの詳細をよく確認し、台湾での安全で快適な移動基盤を築きましょう。
Part 4:台湾での安全運転アドバイス
台湾での運転において日本の常識とは異なる部分もあります。
◆ 右側通行・左ハンドル: 慣れるまで時間がかかります。交差点での右折・左折時、特に慎重に。
◆ バイクの多さ: 車線変更や右折(日本でいう左折)の際に、死角からのバイクの接近に細心の注意を払ってください
◆ 駐車のルール: 路上駐車の規制や有料駐車場のシステムが日本と異なります。特に駐車禁止エリアには厳重な注意が必要です。
これらの注意点を踏まえ安全で快適な台湾ドライブを楽しんでください。
★ 駐在員・車両管理担当者様へ
台湾での駐在生活において、車両の調達や管理業務の負担を軽減するために、外部の専門企業を活用することも一つの方法です。
日系企業向けの支援実績を持つ統一東京(東京センチュリーグループ)では、日本語対応による法人向けカーリースサービスや事故対応、帰任時の車両返却支援などを提供しています。
詳細は以下お問い合わせ先までご連絡をお願い致します。
お問合せ先:
電話:02-2747-8188内線6724 担当:守屋 (もりや) Email : nikkei@ptcl.upeg.com